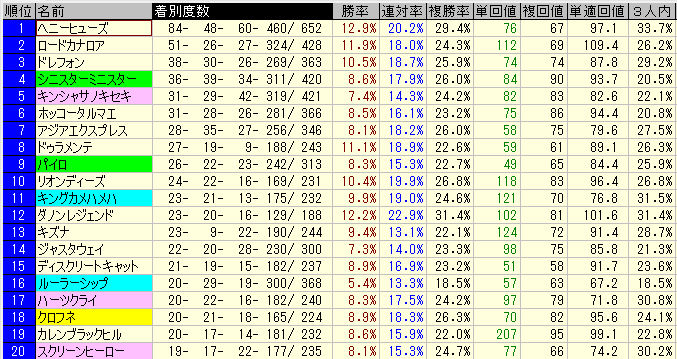中山競馬場
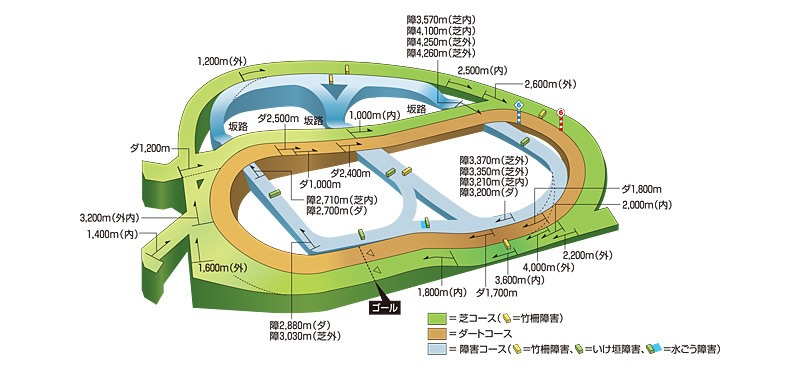
中山ダートコースの解説
基本情報
- 全体の高低差: 5.3m(日本の競馬場で最大)
- ゴール前直線の上り: 2.5m(東京、阪神、中京と大差なし)
コースの特徴
- 早め早めの競馬:
- 短距離ではスタートからゴール直前まで下りが続くため、ハイペースになりやすい。
- 最後の上り坂が存在することで、内・外回りともに5.3mを既に1回上がっているため、最後の坂が堪える。
- 向正面の下り坂により、早めの競馬が強制され、短いゴール前直線でも先行・差しが伯仲しやすい。
排水性の改善
- 排水管の設置:
- 外回りの2角と3角に横断排水管を設置し、排水性が劇的に改善。
- 工事前は重馬場になるところが、工事後は稍重まで収まるようになった。
コースローテーション
- ローテーションの特徴:
- 中山の芝コースは、他の競馬場と異なり、秋競馬をBコースから始める。
- 具体的なローテーション:
- 9月4回中山前5日: Bコース
- 12月5回中山
- 1月1回中山全9日: Cコース
- 3月2回中山全8日: Aコース
- 4月3回中山前2日: Aコース、後4日: Cコース、全8日: Aコース、後6日: Bコース
芝の状態と開催
- 芝の状態:
- 中山は春の皐月賞開催後に休みがあり、養生期間が長いため、秋開催前の芝の状態が良い。
- 過去には春時期に芝が傷むことが多かったが、2014年の改修工事以降、排水性が改善され、芝の状態も安定。
内を突く馬の有利性
- 内有利の傾向:
- 5回中山の最初は内の芝が良く、内有利とされるが、グリーンベルト開催の影響で馬が集中し、外が有利になることもある。
- 有馬記念では、直線に向いた際に馬群がバラけるため、内側が意外と温存されており、内を突く馬が穴馬になりやすい。
まとめ
中山ダートコースは、高低差や排水性の改善により、特有の競馬が展開されます。特に短距離レースでは早めのペースが求められ、内を突く馬が穴馬として注目されることが多いです。コースローテーションや芝の状態も考慮に入れることで、レース戦略や馬選びに役立つでしょう。
- 騎手データ
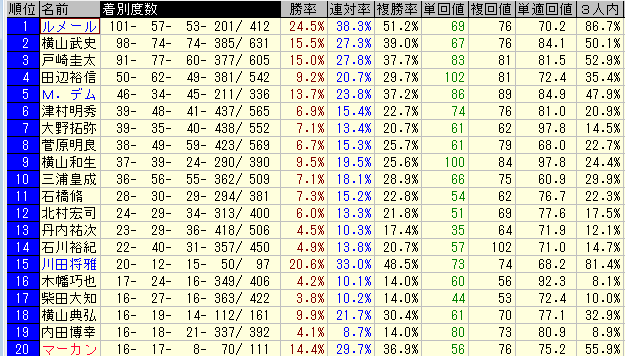
- 調教師データ
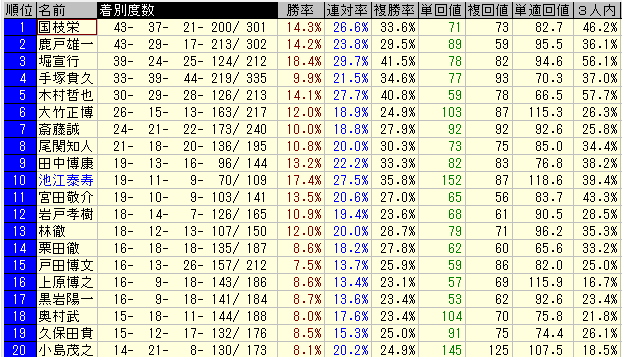
- 馬主データ

- 種牡馬データ
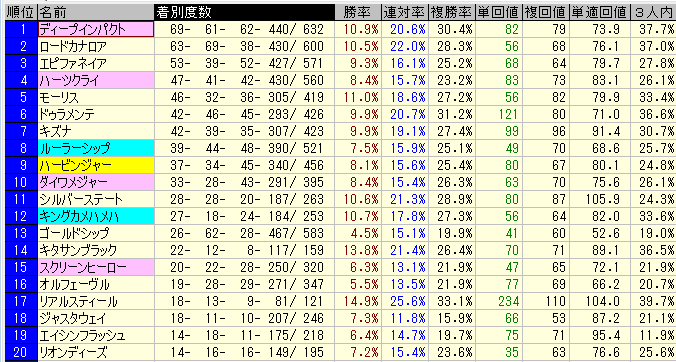
中山ダートコース解説
基本情報
- 1周距離: 1493m(中央4場のダートでは最小)
- ゴール前直線の長さ: 308m(中央4場で最短)
- 高低差: 4.5m
- 幅員: 20〜25m
- 砂厚: 9cm
コースの特徴
- 規模的特性:
- 中山ダートはローカルダートの親玉的存在で、札幌、函館、新潟よりはやや大きい。
- ゴール前直線が308mと短いため、スピードが求められる。
- 起伏の多さ:
- 最大高低差4.5mで、起伏に富んだコース。地方競馬では盛岡ダートが4.4mで続く。
- 向正面は下り、ゴール前直線は入口から上り坂が始まるため、ダートではだらだらとした傾斜が特徴。
ゴール前直線の特性
- 加速とパワー:
- 芝のようなメリハリのある凹凸がないため、ダートでは直線入口から加速が必要。
- パワーが求められ、最後まで押し切る必要がある。
外有利の傾向
- スタート地点の影響:
- D1200ではスタート地点が芝のポケットにあり、外の馬が芝を長く走るため外有利となる。
- データ的にも外枠の成績が良く、D1800でも同様の傾向が見られる。
- コーナーのバンク角:
- コーナーに近いゲート位置が外枠有利の要因。コーナー部分のバンク角が大きく、外の馬が内を見ながらレースしやすい。
凍結防止剤の使用
- 冬場の対応:
- 冬の開催時に凍結防止剤を散布することが多く、特に1月と2月に行われる。
- 凍結防止剤によって砂が粘つき、力が必要になるが、最近の開催では時計変化が確認できなかった。
まとめ
中山ダートコースは、その小さなサイズながらも起伏に富み、外有利の傾向が明確です。特に冬場の凍結防止剤の影響や、コースの特性を理解することで、レース戦略や馬選びに役立てることができます。
- 騎手データ
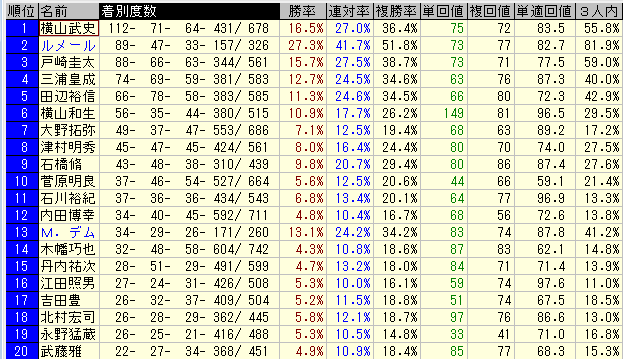
- 調教師データ
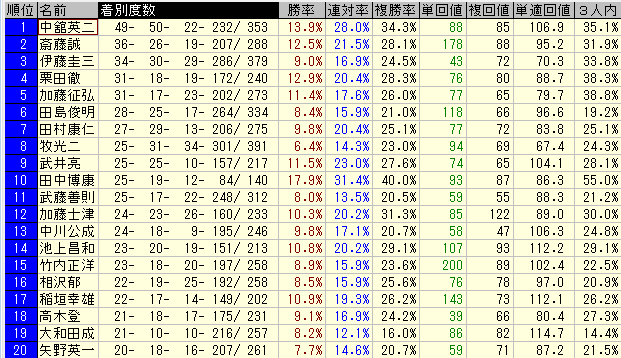
- 馬主データ
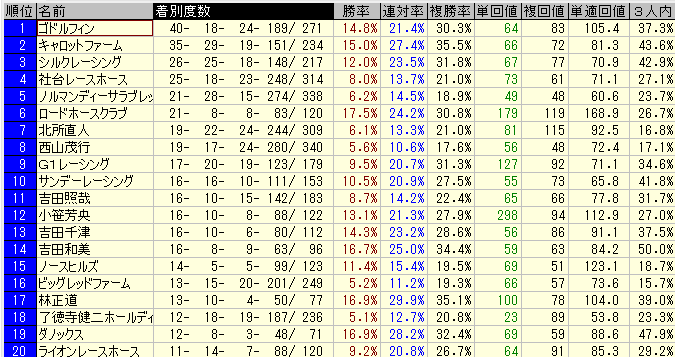
- 種牡馬データ